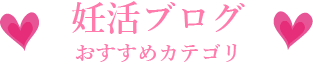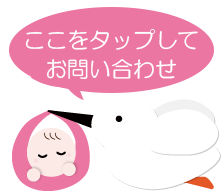低温期しかない?排卵後に高温期にならない原因

基礎体温から妊娠しているのかの目安がわかります。妊娠すると基礎体温表グラフより高温期が続いていくことから判断できるのですが、低温期なのに妊娠するといったことってあるのでしょうか?
実際は低温期なのに子供ができるという事はあり、一体どういうことなのか見ていきましょう。
また排卵後に高温期にならない、2相にならないという事はどういうことなのかをみていってみましょう。
妊娠の仕組みと低温期・高温期
妊娠しやすい時期は、排卵日の3〜4日前から、排卵後の1〜2日の間というのは、妊娠しやすい時期といわれています。
妊娠しいやすい時は卵巣より飛び出して出てきた卵子と精子が出会えると受精し、受精卵が子宮内膜に着床していくことで成立していきます。
基礎体温で、なぜ妊娠したのかという目安がわかるのは、妊娠後はプロゲステロンの分泌が継続し、通常は高温期が平均して、黄体期は10から14日間維持されていきます。(1)
排卵がおこると低温期から高温期へと移行し2相の基礎体温表ではグラフを描きます。
基礎体温表のグラフからわかる妊娠の目安

女性ホルモンが整っている場合は基礎体温をつけていると、生理が始まってからはエストロゲンの分泌により低温相を維持し排卵に向け準備が進んでいきます。その後、低温期だった体温が、ぐぐっと上がり高温相に入っていき、2相のグラフを描くようになります。
これが排卵のサインであり、この移行するどこかで排卵がおこるといわれています。
体温が低かった最終日の前後4 〜 5日間が排卵期となり、妊娠しやすい時期といえます。
しかし、基礎体温のグラフが2相にならずに低温期がそのまま続くという場合もあります。
いったいどういう事が原因でおきているのか見てみましょう。
排卵後に高温期に移行しないのは【無排卵】が原因

通常では、排卵後に基礎体温が上がり低温期から高温期へとシフトしていくのに、低温期のままであるという場合には原因があります。
卵巣の中で卵胞が充分に成長できずに排卵にまで成長できなかったという場合や成熟しても排卵がおこらないといういわゆる「無排卵」である可能性が考えられます。
一般的には排卵後はプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が増えていくため、その黄体ホルモンの働きによって基礎体温があがり、高温期に突入していきます。
しかし、無排卵の場合は黄体ホルモンの分泌量がほとんど増えていかないままなので高温期にならずに低温期の単層のままとなってしまいます。
そのため、低温期と高温期という2層の基礎体温表のグラフが見られず、ずっと低温期のままということになります。
低温期なのに妊娠することって可能なの?

無排卵によって低温期を維持しているという場合は、やはり排卵がおこっていないため妊娠することは不可能です。
ただ、ホルモンバランスによって排卵がおこって高温期に移行していくという経過があるため、ストレスや過労など負荷がかかった場合は
ホルモンバランスが乱れたままという事もあります。
通常は基礎体温では、低温期と高温期の差が0.3~0.5度であると言われています。しかしその差が0.3度以下である場合は無排卵となっているの可能性もあります。
そのため無排卵のままでは妊娠することはありません。また中には、低温期と高温期の差がほとんどないけれど、排卵をしているのにずっと低温期の状態が続いているかのように見えてしまうというケースもあります。
そのため、しっかりと排卵していることがわかれば妊娠できる可能性はあります。
妊娠の兆候としていったん体温が下がることも

基本的には、妊娠すると高温期が持続していくのですが、しかし、妊娠の兆候として体温が一度下がることもあります。
着床時に基礎体温が下がることもあるようです。
ちょうど受精卵が着床する時期に体温が下がったという体験談もあります。おおよそ高温期の7日目から10日目ぐらいに0.3℃ぐらい下がる人が多いようです。
低温期に戻って妊娠しなかったかな?と思っても妊娠していたという事がおこりうるという事ですね。
さらに、着床時出血(着床出血)といって受精卵が着床するときに出血を起こすことがあります。出血量自体はごく少量から生理2日目ぐらいの量で個人差があります。
日本産婦人科学会によると、着床出血というのは、一般名で正式には「月経様出血」と呼ばれています。体温だけでなく、出血まであったら、生理がきたと勘違いしてしまう事もあるでしょう。
月経様出血といって、予定月経の頃に少量の出血があることがあり、
これを生理と思いこむと妊娠に気づくのが遅れることがあります。
しかし、高温期がそのまま持続する人も多いので、基礎体温の変化は個人差が大きいです。そして着床時の症状には個人差がありますので、必ずしも体温が下がるということでもありません。
基礎体温を測り間違えているという可能性

一般的には妊娠している状態は基礎体温が高い状態なのですが、高かったり下がったりガタガタしたりと様々な事もあるかと思います。
そういった場合、基礎体温そのものを正確に測れていないという可能性もでてきます。
そのため本当は高温期なのに低温期に測定値がでてしまい、低温期で妊娠したということになってしまうこともないわけではありません。
基礎体温が、上がったり下がったりを繰り返すときは、基礎体温の測り方が間違っているかもそれないので、一度確かめておくとよいでしょう。
明子ウェルネス・クリニックのホームページによると
婦人体温計を枕元に置き、片手を伸ばせばすぐ届くようにしておいてから、休みます。
ぐっすり、熟睡して目覚めたときに体温計をとり、舌下(舌のうらがわ)にはさんで体温を測定します。
この際、上体をむくっと起こして体温計をとるなどしてはいけません。
手だけ動かして体温計をとるように、よけいな運動をしないように気をつけます。
低温期と高温期の差が少なくても排卵あれば妊娠も

そのため、もともと体温が低い方の場合は排卵後も低温期が続いていると思っていたら、実はきちんと高温期が来ていたという妊娠という事がおこります。
またそういったケースも意外と多いといいます。
平均的な高温期の基礎体温は36.7~37.0度であると言われていますが、もちろん個人差があり、必ずしも基準値内におさまらないという事もなく、そうでなくてはいけないということもありません。
もちろん理想的にはある程度基礎体温は高い方が代謝が活発なあらわれで好ましいのでしょうが、高温期でも36.5度以下の方もいます。
自分のグラフを見た時に、低温期と高温期の温度差があまり見られない場合というのもあるものですが、排卵をしていないという場合は放っておいてはいけません。
平均的な数字に惑わされず、自分の基礎体温値を基準に考えることが大切です。
排卵をしているのかどうかというのは基礎体温表だけで判断せずに、排卵検査薬と合わせてみたり、心配な場合はホルモン値の検査や超音波検査で排卵の有無を見てもらうという選択もあります。
黄体期が正常でも短いこともある
高温期を示す黄体期は、プロゲステロンが多く分泌されるときです。
高温期は12日から14日の間ですが、最短で8日間、最長で16日間あることもあります。通常の黄体期の長さには個人差はあるものの、周期ごとに一貫してその長さになる傾向はあるようです。(1)
8~10日より短い黄体期は、生殖能力にトラブルがあるかもしれません。
でも、必ずしもそうとも言い切れない部分もあり、基礎体温だけで判断はできません。
ただ、流産の繰り返しや不妊女性は、黄体期が短くなる傾向がありますが、受胎能力の高い女性も黄体期が短い可能性があるようです。(2)
通常の生理周期ではプロゲステロンが分泌されていて、着床などに関わるのは他のホルモンの影響も受けている可能性がある
ため、ただ黄体期が短いというだけでは不妊の原因だとは言い切れないようです。(3)
黄体期がなくなってしまう原因とは
黄体期が欠損してしまう原因としては、以下のものが関連しているといわれています。
黄体期の欠陥に関連する考えられる症状または問題には、次のものがあります。
黄体期の欠陥の考えられる原因は次のとおりです。
まとめ
妊娠するには、排卵しているという事が重要な条件になっていきます。
女性ホルモンエストロゲンの分泌が高まっていかないと卵子が育たず、排卵障害、受精障害につながっていきます。また卵子の質が悪いと受精後も育ちにくく、流産や死産の確率も高まるため、低温期だけど妊娠できる可能性もあるなら安心と思わずに、しっかり排卵しているかは見てもらいましょう。
高温期がないというのはやはり少なからず不妊とも関係があります。無排卵の原因となってしまうストレスや不規則な生活習慣の見直しは
欠かせないので、整えていきましょう。







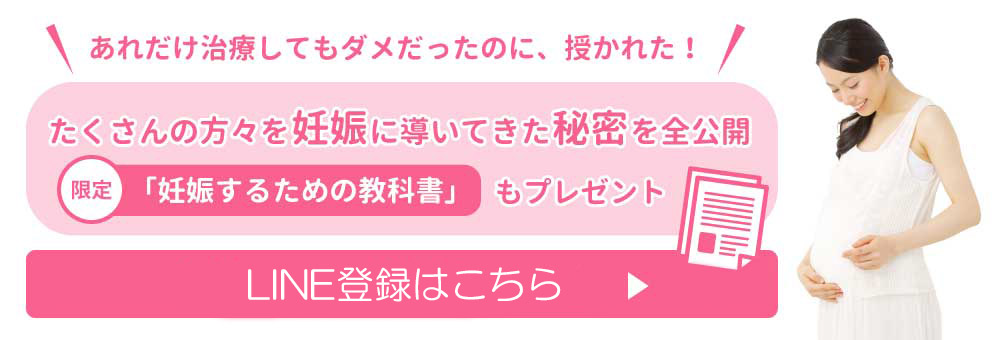

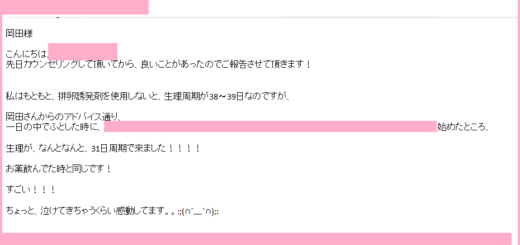






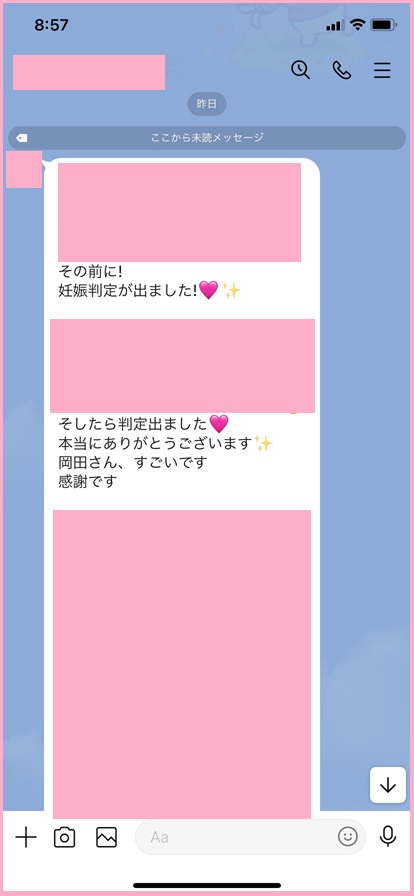 40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告
40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告 妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう
妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう オンライン限定 個別の妊活セミナー
オンライン限定 個別の妊活セミナー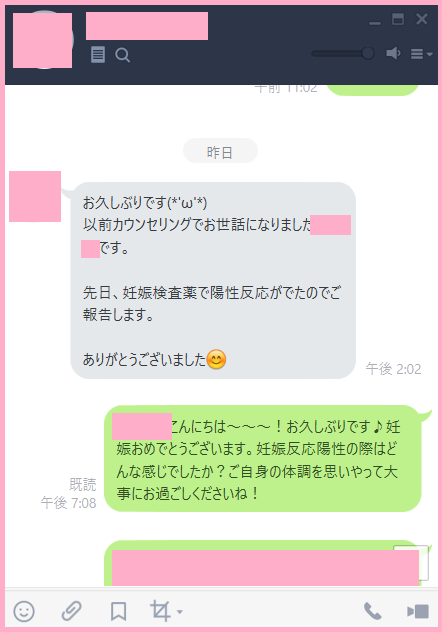 カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事
カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事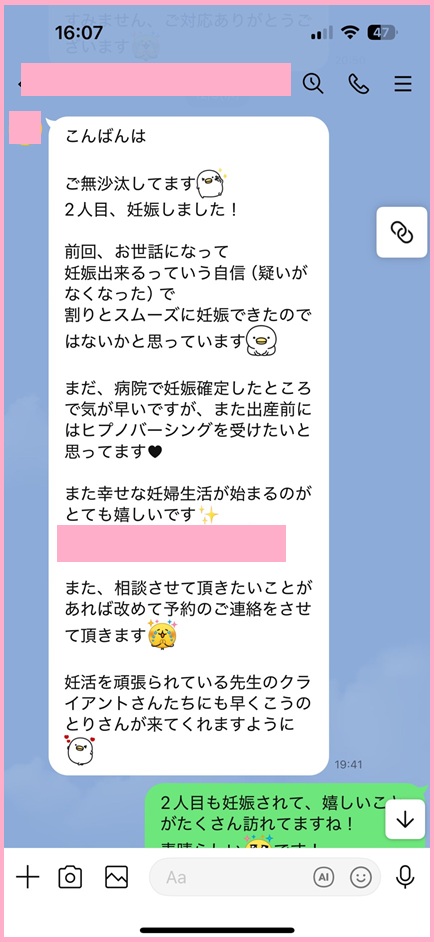 二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!!
二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!! 不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響?
不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響? 原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ
原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ  まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント
まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント 絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント
絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント